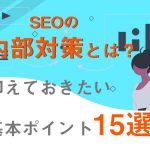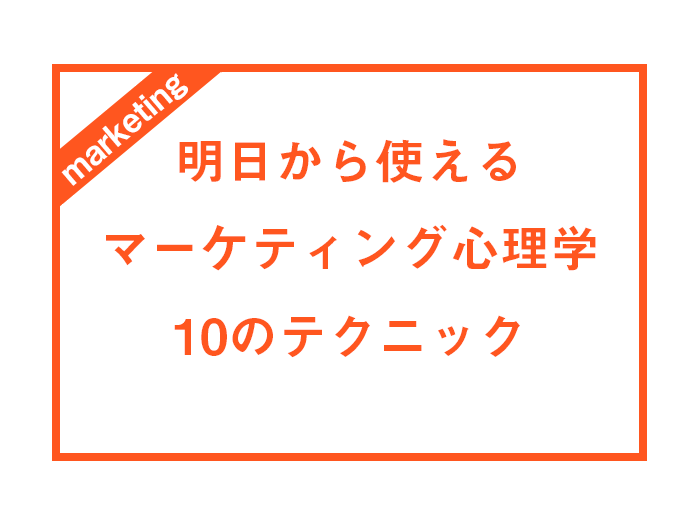
皆さんはマーケティング心理学という言葉は知っていますか?
有名なところでいくと刑事ドラマなどでも使われるサブリミナル(意識下)効果があります。
これは画像や文字を認識できないほどの表示時間であっても、知らないうちにその人の潜在意識に働きかけ、行動や心理的な考え方に影響を与える効果です。
まれに「あの広告は実は秘密が隠されていた!!」といったようなうわさ話が流れたりしますが、基本的に広告業界では暗黙の了解としてタブー視されているものとなります。
マーケティングの業界ではこういった「どのようにすれば人々の行動を喚起できるのか、変容させられるのか」という観点から様々な心理学が使用されています。
サブリミナル効果のように無意識のうちに行動を操作させようとするやり方はほとんど倫理的に行われていませんが、「マーケティング心理学」を使用することで自社の商品の魅力をより深く伝えることができるのです。
このページでは、ビジネスのSEOなどのマーケティングに役に立つ心理学的テクニックを10個紹介していきます。
より深く知りたいと思ったあなたは最後におすすめの心理学の本を紹介するのでチェックしてみてください。
マーケティング心理学10選
カクテルパーティー効果
パーティーやコンサートのような雑多な場所でも、遠くから呼びかけられた自分の名前を聞き分けたり好きなメロディが流れてきたらはっきりと聞こえる。このような経験をしたことはないでしょうか。
このように多くの情報から「自分に都合がよく、自分に関係すると思う部分だけ聞き取る」脳の動きを「カクテルパーティー効果」と言います。
これは広告のクリエイティブや見出しに使える手法で「40歳女性のあなたへ」や「彼氏の行動に不満を感じるあなたへ」といったように
対象を絞ることで見たユーザーが自分のことを言われていると感じより関心を持つ効果があります。
反対に、「みんな」「方々」といったワードは全員に向けている言葉として「自分には関係ない」と興味を失いやすいと言われています。
ハロー効果
ハローとは「後光」を表す言葉。ある分野で特殊な技術を持つ人がメディアに取り上げられ、これまで修めた学問や出身校などその人のバックボーンでよりその人物が魅力的に見えることを「ハロー効果」と言います。
人は何かに対して価値を感じるときに特定の面のみならず、トータルで判断する傾向にあります。
「ニュース番組に登場するあのアイドルはあんな私立有名大学を卒業している!」
「この商品はあんな有名芸能人も使用している!」
といったことでより興味を感じるのではないでしょうか。
このように商品に関しての魅力を伝えるだけでなく、美人タレントも使用中!あの有名企業がOEM供給されている!など複合的に明示することで効果的と言えるでしょう。
ウィンザー効果
商品に対して利害関係がないと思われそうな人が商品に高評価していると、不思議にその評価を信じてしまうことはないでしょうか。
通販サイトなどの口コミはそういった第三者的意見は受け入れてしまう、そんなウィンザー効果を狙っています。
商品やサービスの説明をする際にも「お客様の声」「口コミ」といった第三者の意見のようなものを記載することで、より評価を高められるでしょう。
松竹梅の法則
特に日本人に顕著といわれているのが、類似商品が並んでいると真ん中の金額を選んでしまう現象、「松竹梅の法則」です。
一番高い商品Aと少し安い商品Bを比較すると「ここまで高性能でなくていいから、商品Bを選ぼう」とユーザーは判断し、また更に安い商品Cに対しては、「せっかくだしちょっと性能のいい商品の方がいいか」と判断しやすくなるのです。
ここ数十年で、ユーザーはより商品金額によって購入決定をする傾向にあるため、本当に売りたい商品よりも高額な商品を明示することで効果が得やすいと言えるでしょう。
決定回避の法則
大型家電量販店やドラッグストアで何を購入しようか迷って何時間もお店にいたなどの経験はないでしょうか。似たような商品がいくつもあって違いが少しづつだと見る側は選ぶこと自体億劫に感じ、購入を控えてしまう可能性が出てくるのです。
この法則をしっかりと考慮したマーケティングが(かつての)appleです。
メイン商品であるスマートフォンのラインナップは二種類に抑え、ユーザーが購入する際に判断する違いを抑えることで「ここの機能が欲しい、ならこっちの商品だ!」「この機能は使わない、ではあっちの商品だ!」と判断しやすくしているのです。
シャルパンティエ効果
有名な問題で、「鉄1㎏と綿1㎏はどっちが重いでしょう?」という問題を聞いたことはありませんか?ついつい「鉄1㎏!」答えてしまったりしていないでしょうか。
これがシャルパンティエ効果といって比較対象の物質を置き換えることによって、商品から得られる効果をより打ち出そうとする手法をいいます。
よくテレビCMで「レモン○○個分のビタミンC配合!」という文言を見たことがあると思いますが、レモンがいくつ分あれば体にいい影響があるのか、そもそもレモン一つにどれほどビタミンCが含まれているのかほとんど理解している人はいないでしょう。
しかしもともとのビタミンCが入っているというイメージからビタミンCと比較することで効果が高い印象を与えることができるのです。
カリギュラ効果
「この箱は絶対に開かないでください」
そう言われた浦島太郎も最後に箱を開いてしまいます。
これがまさにカリギュラ効果です。
人は何かを禁止されたとき、余計にそれが気になってしまう心理効果を「カリギュラ効果」と言います。
広告のキャッチコピーで「○○な人は絶対に見ないでください」と記載されているとまさにこの効果を狙っていると思っていいでしょう。
「悪用厳禁!」というワードが書かれている記事もついつい気になるようにかかれているわけです。
アンカリング効果
これまたマーケティング心理学で有名なアンカリング効果は、最初に見たものがその後の判断に影響を及ぼすという心理効果です。
似たような商品でもAという定価3,000円の商品を定価15,000円から80%引きで販売しています!と書くと売れたという例があります。
3,000円という価格を見ても人はそれが適正価格なのか、それとも割高なのか判断できません。そんなときに過去買った同じような商品を思い出し、「前買ったコップは1,000円だったから3,000円は高いな」と判断するのです。
そこで15,000円という新たな基準をユーザーに提示することでお得感を植え付けることができるのです。
認知的不協和
認知不協和とは、自分の中で矛盾する二つの事柄を同時に抱えた場合、ストレスを抱えるという心理現象です。
「教科書からは何も学べない。」
「偉い人が言うことは何も聞くな!」
このような文言を見るとそれまでの常識や価値観を否定するようで、そこで生まれた矛盾を解決しようと人は解決する方法を探すようになります。
そこでより詳細を読ませることができるのです。
テンション・リダクション効果
最後はテンション・リダクション効果です。
この心理効果はつまり、緊張状態がほどけて気が緩んだ時に決断力が薄れる状態を指します。
アクション映画などで敵に襲われ間一髪でかわした後、ほっと一息ついたところで別の脅威に襲われ痛い目にあうといった内容をよくあるシーンではないでしょうか。
これはECサイトをよく利用する方はよく体感するもので、「ああ、あれね!」と感じることができるはずです。
ECサイトで時間をかけて商品購入をした後に「こちらを買った人はこちらも一緒に良く買われます。」「こちらもご一緒にどうですか。」といった表示が出てくるかと思います。
これは大きな決断して一息ついた瞬間のユーザーの気が緩んでいる時を狙った売上を伸ばす手法だったのです。